
SNSの正しい利用について学ぶメディアリテラシー講話を6月6日(水)に行いました。松本警察署スクールサポーターの吉田さんから、「簡単に利用できるSNSだからこそ、簡単に被害者にも加害者にもなり得る」「子どもにも大人にもSNSを適切に利用する責任がある」といった趣旨のお話をお聞きしました。
講話ではほかにも、子どもにも自分で心身を守る権利がある/簡単に大金を手にできるようなバイト募集はありえない/迷惑行為や不適切な行動は他者が見ていることを忘れないで―など、注意しなければならないことを教えていただきました。
管内でも多くの事案があるそうで、日頃報道などで目にしていることは、すぐ身近にある現実なのだと実感しました。そして、14歳ともなれば、例えば「闇バイト」に加担したことが分かれば逮捕にいたると聞き、生徒はドキッとしたような表情も見せていました。
吉田さんは、ご自身が車の運転中に遭遇した危険な場面も話題に挙げました。
冬、雪道を歩いていた学生グループの中の1人が転倒。吉田さんはとっさにブレーキをかけ停車しましたが、学生たちは転倒した子の動画撮影に夢中で、車の存在には気づいていない様子だったそうです。
「この場合、まずは救助と安全な場所への移動が最優先。大きな事故になっていたかも、と大変怖い思いをした」といい、「"なんとなく"・"面白いから"・"軽い気持ちで"した行為が、どれだけ多くの人に迷惑をかけることになるかを考えていない。過ちの責任は自分にあり、子どもだから許されるものではありません」と、厳しいお話もされました。これは、公私関係なく、いつでもあてはまることです。
生徒代表者はお礼とともに、「SNSに振り回されない判断力と知識を持って、犯罪に巻き込まれないようにしたい。家族ともしっかり相談したい」と挨拶。
ある生徒は、教材動画(SNSで知り合った人から、自分のプライバシーが不特定多数の人の目に触れることになった)に顔をしかめたと言い、「自分はそうやって人と会うことはしないと思うが、相手の存在、考えていることとかが嘘か本当かわからないと、とても不安」と話していました。
時間の最後、まとめのお話にあった「ネット利用に必要な3つの力=判断力・自制力・責任力」をしっかり養って、安全かつ楽しく利用できるよう努めたいです。
 「みなさんのような小中学生も、いつ犯罪に巻き込まれるかわからない」と吉田さん
「みなさんのような小中学生も、いつ犯罪に巻き込まれるかわからない」と吉田さん
 メモを取りながら話を聞く生徒
メモを取りながら話を聞く生徒
体育祭後の休業日が明けた5月29日(水)、全校集会が行われました。校長からは各学年に向け、労いと称賛の言葉が送られました。また、昨年度分も含めた表彰式があり、部活動で1団体、個人2名が全校の前で校長から賞状やメダルを伝達されました。
【校長講話】
第19回体育祭は、最後の大玉送りまで勝負が分からないほど盛り上がり、才教らしい行事でした。一人ひとりが自分の競技に全力を尽くし、応援に全力を尽くし、裏方では係の仕事に全力を尽くした。すべての全力がかけ合わさって、才教生が持つ力のすごさを見せつけられました。
低学年のみなさんは、小さい体で一生懸命に練習してきましたね。開閉会式で「気をつけ」の姿勢でじっと立つ1年生を見て、本当の才教生になったなと感じました。
2年生は、遠足やさいきょう商店街などの場面で先輩としての姿を1年生に見せる立場。体育祭で得たこと、学んだことを、学年行事にも活かしましょう。
3・4年生がフィールドを駆けるさまは力強かった。『この1本にかけろ!』では重く長い棒を長時間引き合って、でも「絶対に負けない」という気力が、迫力ある戦いになったと思います。今3年生のみなさんは、来年はどうやって棒引きをやろうかと考えてみてください。4年生は、Ⅱ期生になると競技も増えます。今から体作り、体力作りをしてみるのも一考です。
5・6年生に共通して私が一番感動したことは、行進の美しさ。スローガン『闘』の意図が一歩一歩に込められているようで、胸を打たれました。上級生の競技の時は、赤白ともに下級生をまとめ応援で鼓舞していましたね。才教生として立派に範を見せていました。
7・8年生は、9年生の意を汲み手足となって本当によく動いていました。みなさんが頭で考え、一生懸命活動した事実。それが体育祭の下支えになっていました。一人ひとりが役割を自覚して、それを徹底することでしか、チーム力というものは上がりません。係活動、それぞれにやるべきことを遂行したことが、体育祭の成功につながりました。特に8年生。来年はみなさんが体育祭を作る番です。日頃から、どんな体育祭を創りたいか、才教学園としてふさわしい体育祭とはどういうものか、そんな夢も膨らませてください。
9年生。見事でした。みなさん一人ひとりの働きがあればこその体育祭でした。今年は多くの苦労をし、今まで見えなかった風景もたくさん見えたと思います。9年生が仕切り、先頭に立って後輩を引っ張らなければ、体育祭の成功はなかった。今回の成功を自信とし、次の行事につなげてほしいです。
これからも、いろんな場面で活躍する姿を見せてください。この体育祭を糧に、次のステージに行きましょう。
〖表彰:個人〗
●第35回読書感想画中央コンクール小学校低学年の部
林もろみさん(3年) 奨励賞
●第42回JSBA全日本スノーボード選手権大会
武田理暉くん(4年)
スロープスタイル(U15)優勝
ハーフパイプ(U12) 準優勝
※個人表彰は令和5年度関係分。林さんは2年次、武田くんは3年次にそれぞれ標記の賞をいただきました。
〖表彰:部活動・団体〗
●2024長野県中学校交流テニス大会男子団体戦
才教学園中学校男子テニス部 準優勝
みなさん、おめでとうございます!
信州スカイパーク・やまびこドームで5月26日(日)、第19回体育祭を開催しました。
今年は応援合戦が2部制に、また、全校生徒参加の「大玉送り」が復活と、コロナ以前の競技もありました。例年のことながら、競技に臨む生徒たちは『闘~鼓舞せよ、才教魂~』のスローガンのもと、「勝ち」にこだわり熱い戦いを見せてくれました。
「練習では勝っていたのに本番で負けた」とがっかりしたり、逆に「全然勝てていなかったけれど、当日は見事に勝てた!」と歓喜に沸いたり・・・競技の勝敗によって悲喜こもごも。前半は赤組が大差でリードしていたものの、結果として、得点対象となる12競技のうち8競技で赤組を上回る成績を収めた白組が今年の総合優勝を勝ち取りました。
閉会式の結果発表では嬉しそうに飛び跳ねる白組の生徒たちの姿が見られました。その横で、悔し涙を流しながらも爽やかな拍手で称えた赤組。どちらも本当に素晴らしい闘いぶりでした!

遅ればせながら、その生徒たちを支え、声援を送っていただきましたご来賓と保護者のみなさま、後輩を応援すべく集まってくれた卒業生のみなさんに、深く感謝いたします。そして、練習から本番までお世話になったやまびこドーム管理関係者の皆様にも、感謝申し上げます。みなさま、ありがとうございました







ハンガリー出身のバイオリン奏者、オラー・ビシュモル氏と、ビオラ奏者としてドイツのオーケストラなど世界各国で活動され、日本弦楽指導者協会理事長である立木茂先生によるコンサートを、5月14日(火)に校内講堂で開催しました。
7~9年生を対象に1時間ほどではありましたが、一流の演奏家による豊かな音色が響き、とても贅沢な時間を過ごさせていただきました。

オラー先生は、「音楽は普遍的なものなので、どんな時代でも、どんな場所でも認められるすばらしさがある。すべてを理解しようとするのではなく、心を開いて聴いてほしい」と、母国であるハンガリーの作曲家・バルトークや、バッハ、パガニーニなどの曲を披露したほか、ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」の一節でも楽しませてくださいました。

演奏後、コンサートのコーディネーターとして一緒に来校された小林あや先生(長野県議会議員、本校評議員)がリードするトークセッションで生徒の質問に丁寧に答えてくだったお二方。
「自分も聴く人も楽しくないと意味がない。楽しそうな顔が見えると嬉しい気持ちになるし、そういうときを目指して演奏しています」と話された立木先生。
真摯に、懸命に物事に取り組むからこそ、周りに感動を与えられる・・・ということで、間もなく行われる体育祭にも、秋のさいきょう祭にも、通じる部分がありますね。
すてきな演奏に加え、大切なことを教えていただき、ありがとうございました。

《生徒の感想》
●ヴァイオリンとヴィオラの違いを直接知ることができた。二重奏では違う高さの音か生まれる美しいハーモニー、ソロでは、演奏者の気持ちを読み取りながら聴くことができた。トークセッションで、『考え(脳)、心(気持ち)、技術(指)、教育の4つが大切である』とオラ--先生が言っていた言葉が心に残った。4つのうち何か1つが欠けていたり伸びすぎていたりしていたら、物事はうまくいかない。どんなことでも、この4つをバランスよく保てるようにしたい。
●久しぶりに聴く弦楽器の演奏は迫力がありつつとても繊細で、聴いていて心地よかった。アイコンタクトで気持ちを伝え合っているのが分かり、それに答えるように演奏しているのもすごいと思った。小さい頃から歌っていた『信濃の国』が、演奏だけなのに、自分たちで歌うのと比べものにならないくらい凄かった。
●バイオリンとビオラは、弦が1本分違うだけなのに音が結構違うということが分かった。バイオリンのスピッカートの弾んだ感じが個人的に好きなところ。それに、演奏が終わった時に弦を持っている手を上に上げる動作が綺麗だなと思った。立木先生が最後におっしゃった、「音楽は自分も相手も楽しめるようにしないといけない」という言葉に考えさせられた。遠くハンガリーから来ていただき、素敵な演奏にとても感動したし、楽しいコンサートだった。
5月9日(木)、1年生を対象に、不審者に声をかけられた場合の対応について学ぶ防犯教室を行いました。
松本警察署安全課・スクールサポーターの方から、先ずは「こんな人に気をつけよう」「こんな言葉に気をつけよう」というお話がありました。その後、声をかけられたり車に乗せられそうになったりしたときに取るべき行動について、生徒がロールプレイで疑似体験。また、ランドセルを背負って防犯ブザーを鳴らす練習では、「危険な時は、ランドセルを捨てていち早く逃げるように。命より大切なものはありません」と教わりました。

子どもたちは、終始真剣に考えたり、クイズに答えたりしながら、懸命に取り組んでいました。
小さな1年生でも、できる限りの知識を持ち、とっさの時に自分の頭で考えて、「自分の命は自分で守る」ことができるようにしなければなりません。
講師の先生のお話にあった、「大きな声で挨拶をする子は、不審者から狙われにくい」というお話も興味深いものでした。「もしも」の場合に備え、日々の学習や普段の行動の仕方が大切になりますね。
知らない人、あやしいなと思う人から「道を教えて」「○○をあげるよ」「車に乗せてあげるよ」などと声をかけられても絶対に応じず、『いかのおすし』の5つの約束を守って、子どもたちが安心安全に外出、登下校できることを願います。
今年度がスタートして2週目に入りました。
4月19日は3・4年生、20日は7~9年生(中学生)の授業参観があり、多くの保護者、父兄のみなさんに学校の様子を見ていただきました。
「先生、あててください!」と言わんばかりのピンとした挙手。はにかみながらも自分の意見をしっかり伝える真摯な態度。板書を写すために紙の上を鉛筆が走る音。先生やクラスメートの方を見て、話に耳を傾ける姿・・・ トライアル&エラーを繰り返しながら成長していく子ども達の様子を、教室の中でご覧いただけたのではないかと思います。
以下、一部ではありますが、今週の参観の様子を画像でご紹介します。












5年生を歓迎し、委員会や部活動について紹介する生徒会主催のオリエンテーションが4月12日(金)に行われました。
まず、生徒会長・安藤さんが、「生徒会は、自分たちの課題や問題を見つけて話し合い、学校生活をより充実させるための組織。各委員会の紹介をよく聞いて、自分の入りたいところを決めてほしい。また、部活動も大会やさいきょう祭など活躍の場が充実している。興味をもって積極的に参加してもらえたら」と概要を説明しました。
【委員会紹介】
新設のSDGs委員会、福祉委員会を含め、10の委員会があります。委員長らが前に出て活動目標や具体的な活動を紹介し、その委員会ならではの魅力、「こんな人に委員になってほしい!」といったことを元気にアピールしました。




【部活動紹介】
どの部も趣向を凝らした発表で、ときに笑いも起こり大いに盛り上がりました。生徒会委員会とは異なり部活動への加入は任意ですが、興味のある部活へはまず仮入部で参加します。




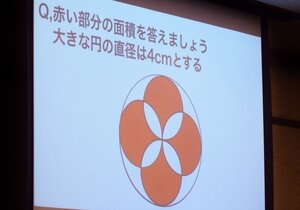

【5年生代表挨拶/金子愛奈さん】
「今日は5年生のためにありがとうございました。新しい制服と共に、全員所属の生徒会活動を頑張りたいし、部活動は勉強との両立を考えて決めたいと思います。分からないことも多いけれど、先輩方に教わりながら全力で取り組みたいです。」

約2時間のオリエンテーションを、終始笑顔で見守った校長先生。5年生に向けて、「今日のことを思い出しながら、自分が入りたいところをしっかり考えて決めてほしい。一人ひとりの学校生活をよりよくするものであり、様々な学びを得られるチャンスがあるので、積極的に参加して」と声をかけました。そしてこの会の運営に携わった9年生を労い、「自分たちの力をいかんなく発揮し、リーダーとしての役割を果たして」と声をかけました。
4月12日(金)の1時間目は、火災を想定した避難訓練でした。芳川消防署から3名の隊員のみなさんが来校され、教職員の誘導や生徒が避難する様子を見ていただきました。
理科室から出火したとの報せに、近くにいた先生たちが消火器を持ち寄って初期消火を試みました。もちろん実際に消火剤を噴射したわけではなく、自教室にいた生徒たちからは見えない場所でのことでしたが、理科室周辺は緊迫した状況でした
全員校庭に避難するようにとの放送が流れると、生徒たちはハンカチやタオルで口や鼻を覆い、身を低くして足早に移動。階段などやや狭いところを通過するときは、時折順番を譲り合いながらもできるだけ早く外へ...と逸る気持ちを隠せない様子でした。
避難完了後は、水消火器で初期消火のデモンストレーションを行いました。隊員の方に指導を受けながら、先生も生徒も真剣に消火器を扱いました。
年度内には複数回、「命を守るため」の訓練の機会があります。いざという時に誤った行動をとらないよう、真摯に取り組みたいと思います。
【講評:消防隊員の方から】
火災発生時、階段を含め建物内では煙で視野が無くなり、においも分からなくなりがち。口元にハンカチなどをあてていると片手でしかあたりを探れないこともあるし、行く先が柱や曲がるところで見えにくいと、他の人とぶつかってしまう。他にも、非常時には防火扉が閉まるなどして「普段はそこにないもの」が現れることもあるので、十分に気を付けて。また、放送がよく聞こえない、聞きづらいといったときは、階段に行ってみるとよく聞こえるはず。特に先生方に、伝達の際に意識してもらえたらと思う。










始業式の後には、2つの進級式が行われました。
《9年生》
Ⅲ期生の証である青いネクタイを贈られた9年生。その節目に激励として、小松校長は例年のように『楕円』をキーワードに講話を行いました。
リーダーの資質は、自分を中心にした円ではなく、異なる考えを持った人と自分との距離を取る、つまり2つの焦点を持つ楕円を描くイメージで物事を進めることが、リーダーの資質として大切なことだと話し、「才教学園の先輩が19年間で培ってきた伝統と、下級生の成長を見据えながら、今自分たちがやろうとしていることとをバランスよく進めるよう邁進してほしい」と、最上級生に寄せる期待を顕わにしました。


《5年生》
つい3週間前までは4年生でⅠ期の制服を着ていましたが、Ⅱ期への進級に伴い真新しい制服に変わった5年生。気持ちも新たに、粛とした雰囲気で進級式に臨みました。小松校長、巣山教頭、担任の先生たちを前に、三澤桜來さんは「Ⅱ期生になった自分は、物事に夢中になり過ぎず自律の心を持てるようになりたい。また、学年として、お互いを尊重して楽しい学校生活を送りたい」と話しました。続けて、今井帆夏さんが、「Ⅱ期での目標は、クラスの全員が楽しく過ごせること。そのために、相手のことを思い、自分から積極的に行動できるようになりたい」と丁寧に挨拶しました。
